面会交流の取り決めとトラブル予防|テンプレ・文例つきガイド2025年版
面会交流は子の利益を最優先に、父母が無理のない運用を合意して続けることが何より大切。この記事は、初めてでも迷わないように、取り決め項目・文例テンプレ・運用ルール・トラブル予防策の流れをまとめました(一般情報/詳細は各家庭裁判所・自治体の最新案内でご確認ください)。
1. 面会交流とは(まず知っておくこと)
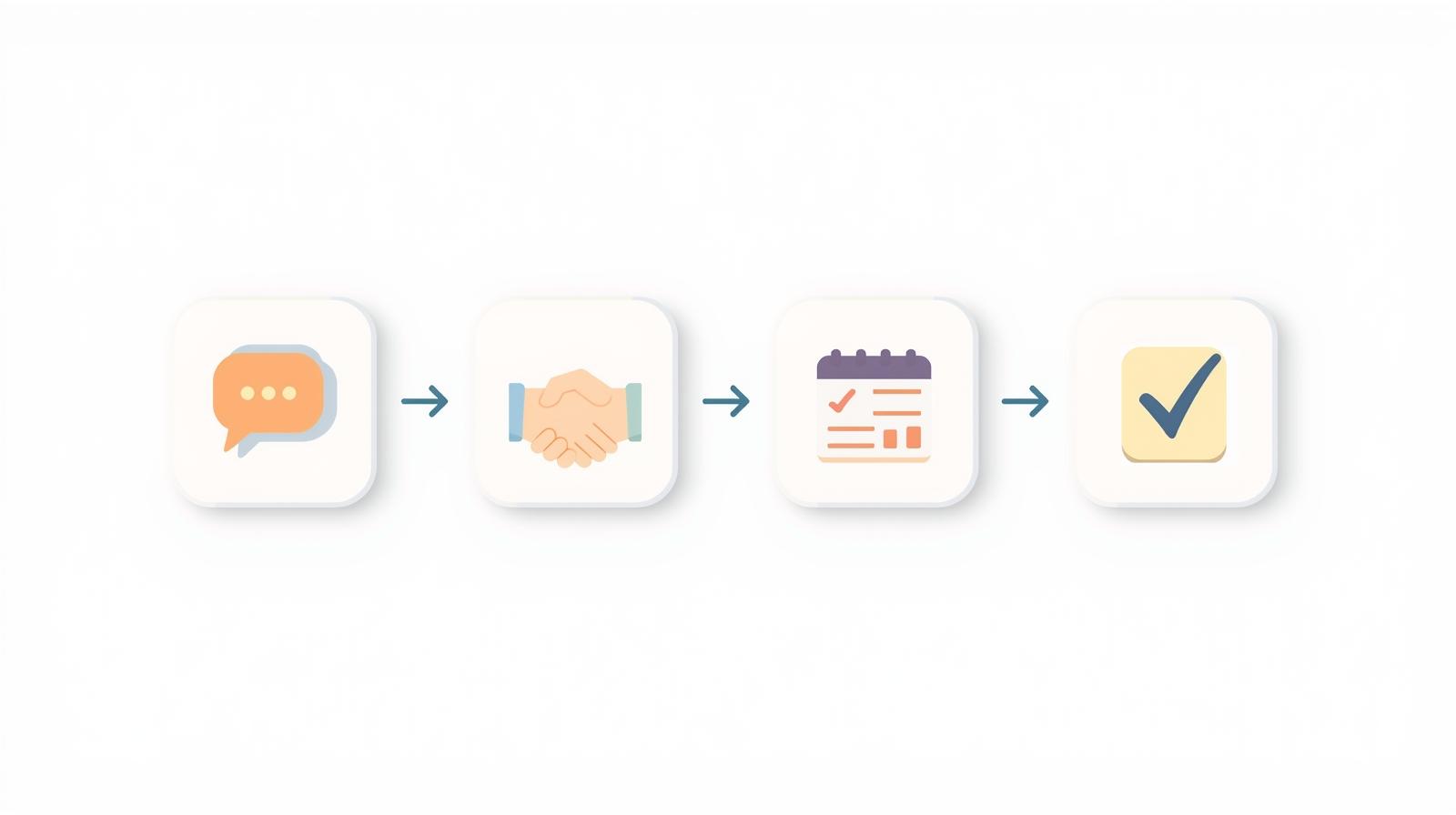 面会交流は、別居・離婚後に同居していない親が子と会ったり連絡をとったりすること。取り決めの中心はあくまで子の健全な成長に資する形であることです。
面会交流は、別居・離婚後に同居していない親が子と会ったり連絡をとったりすること。取り決めの中心はあくまで子の健全な成長に資する形であることです。
話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判で合意形成を支援してもらえます(手続は非公開)。
ひとことポイント:
大人同士の対立は子から切り離す。頻度よりも、続けられる運用を優先。
大人同士の対立は子から切り離す。頻度よりも、続けられる運用を優先。
2. 取り決め項目の基本セット(チェックリスト)
- 頻度・時間:
月◯回/◯時間。宿泊の有無、開始・終了時刻。 - 受渡し:
場所(公共の駅・施設等)、待機場所、引渡し方法。 - 連絡手段:
通常はメール/アプリ、緊急は電話。返信期限(例:24時間)。 - オンライン交流:
ビデオ通話の頻度・時間帯・同席ルール。 - 学校・行事・医療:
行事参加、通院同席の扱い、報告の方法。 - 費用:
交通費・飲食・施設料、負担割合、事前承認の要否。 - 例外規定:
体調不良・天候・災害・受験期の取り扱い、振替ルール。 - 禁止事項:
第三者への引渡し、連れ去り防止、相手の悪口の禁止。 - 安全配慮:
住所秘匿、第三者同席、支援機関の利用条件。 - 見直し時期:
半年/1年ごとに運用レビュー。
3. 合意書・取り決めの文例テンプレ
下記をコピペして、実情に合わせて編集してください。
第1条(目的) 当事者は、子の利益を最優先に面会交流を継続することを目的とし、本合意を定める。 第2条(基本スケジュール) 1 頻度:毎月第1・第3土曜、各2時間(14:00~16:00) 2 場所・受渡し:○○駅○口改札前にて受渡し・引渡し 3 宿泊:現時点では行わない(半年後に再協議) 第3条(連絡手段) 通常連絡は専用メール/アプリ、緊急は電話。原則24時間以内に返信する。 第4条(オンライン交流) 面会がない週は水曜19:30~19:50にビデオ通話を実施。録画はしない。 第5条(費用) 交通費は各自負担。施設利用料は原則申出側が負担する。 第6条(例外・振替) 子の体調不良・荒天・学校行事等で実施困難の場合、相手に速やかに連絡し、 1週間以内の代替日(同等時間)を候補2つ以上提示する。 第7条(禁止事項) 相手方やその家族の誹謗中傷、住所等の詮索、第三者への引渡しは禁止する。 第8条(安全配慮) 受渡しは人目のある公共施設で行い、子の様子に不安がある場合は第三者同席または支援機関を利用する。 第9条(見直し) 半年ごとに本合意の運用を見直し、必要に応じて改定する。
ひとことポイント:
誰が・いつ・どこで・何を・できなかった時はどうするまで文章化。運用=担保です。
誰が・いつ・どこで・何を・できなかった時はどうするまで文章化。運用=担保です。
4. 年齢別の現実解(未就学/小学生/中学生)
| 年齢帯 | 頻度・時間の目安 | 方法の工夫 |
|---|---|---|
| 未就学 | 短時間・高頻度(例:隔週1〜2時間) | 公園や屋内遊び場。受渡しは人目のある場所。宿泊は慎重に。 |
| 小学生 | 隔週〜月2回(2〜4時間) | 学校・習い事のスケジュール優先。オンライン短時間の併用が便利。 |
| 中学生 | 部活・受験で柔軟対応 | 月1回+オンライン、試験期は振替。本人の意向を尊重。 |
5. トラブル予防の運用ルール(実務)
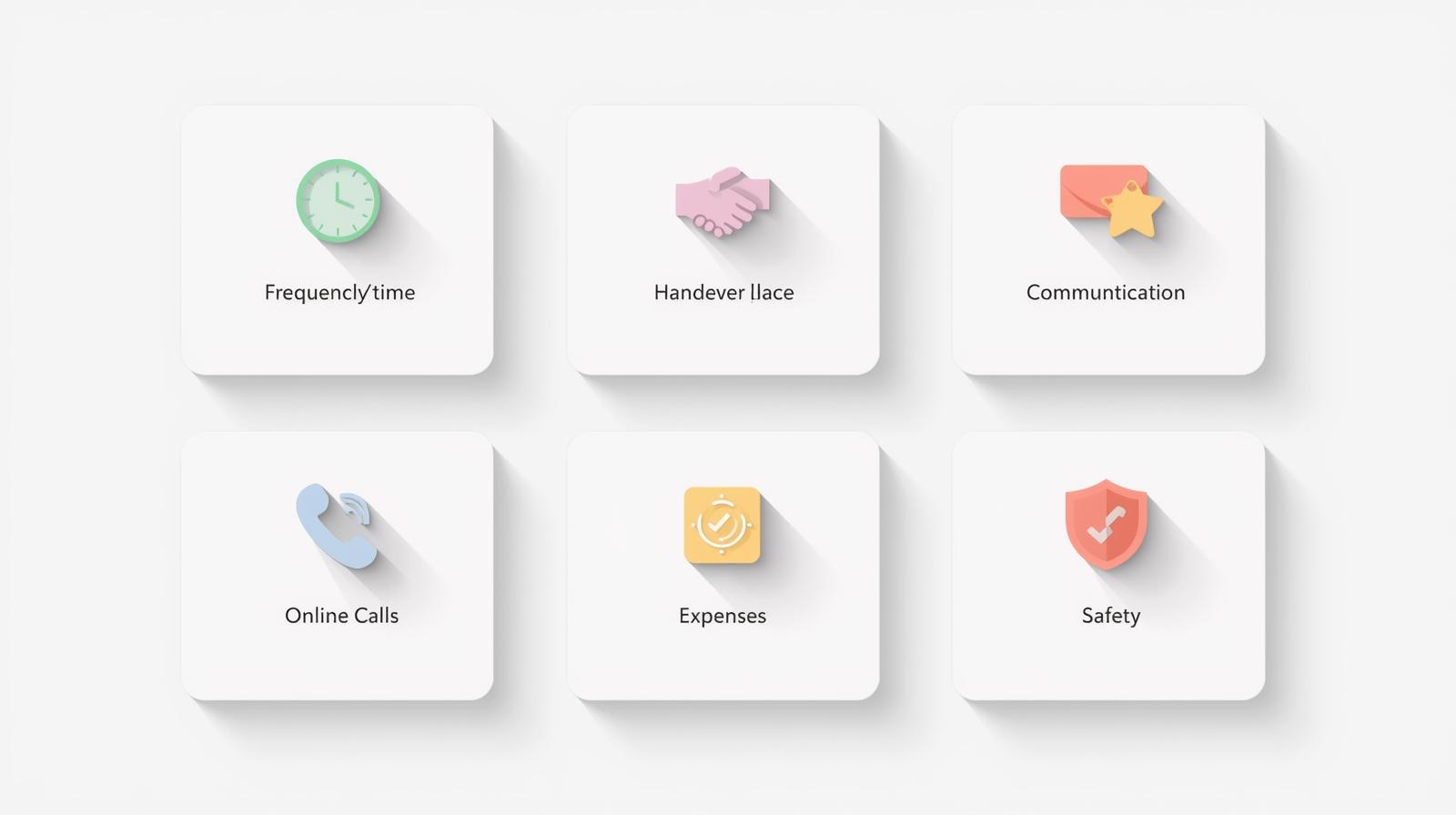
- 共有カレンダー:
Googleカレンダー等に予定を登録、更新履歴を残す。 - 48時間前リマインド:
前々日に実施可否を相互確認。 - 当日報告:
開始・終了時に「受渡し完了/引渡し完了」を一行報告。 - 記録方式:
やり取りは記録が残る手段を基本に(通話は要約をテキスト化)。 - 見せ方の配慮:
子の前で相手の批判をしない。写真・動画の共有は子のプライバシーに配慮。
ひとことポイント:
ルールは短文で。守れる仕組みに落とすと、揉め事が激減します。
ルールは短文で。守れる仕組みに落とすと、揉め事が激減します。
6. できない・遅刻・体調不良時の扱い
- キャンセル:
分かった時点で連絡。1週間以内に振替日を複数提案。 - 遅刻:
15分以上の遅れは即連絡。待機上限(例:30分)を決める。 - 体調不良:
発熱・感染症の疑いは中止、医療後に日程再調整。 - 学業優先:
試験・行事は優先。代替案で調整。
7. 面会交流支援・第三者関与の使い方
安全配慮が必要な場合は、自治体やNPOの面会交流支援(親子交流支援)を検討。第三者同席・受渡し支援・見守り等のサービスがあり、回数や時間の上限、利用条件が決まっていることが多いです。
- 支援の有無は自治体サイトで確認(「親子交流支援」「面会交流支援」)。
- 費用・回数・場所の制限を確認(例:月1回/最長4時間/一年間など)。
- 支援機関の報告書フォーマットの有無もチェック。
8. まとまらない時の公的ルート(調停等)
話し合いが難しいときは、家庭裁判所の面会交流調停を利用できます。申立書式は公式サイトからダウンロード可能。手続では子の年齢・生活リズム・意向などに配慮しつつ、合意点を探ります。
- 申立書、事情説明書、進行照会回答書(各庁様式)
- 非開示(住所秘匿)や第三者関与の運用が必要なときは、庁の案内を確認
9. よくある質問(Q&A)
Q. 別居中ですが、離婚前でも取り決めできますか?
A. できます。話し合いが難しい場合は面会交流調停が利用できます(離婚前も可)。
Q. 共同親権のニュースを見ました。面会交流は変わりますか?
A. 2024年の民法改正で離婚後の親権・親子交流等のルールが見直され、2026年5月までに施行予定です。基本は子の利益最優先という考え方で、面会交流の実務もこの原則に沿って運用されます。最新情報は公的サイトで確認してください。
Q. DVや強い対立がある場合は?
A. 安全最優先。住所秘匿、第三者受渡し、見守り型支援、オンライン交流などを検討し、必要に応じて弁護士・法テラス・家庭裁判所へ。

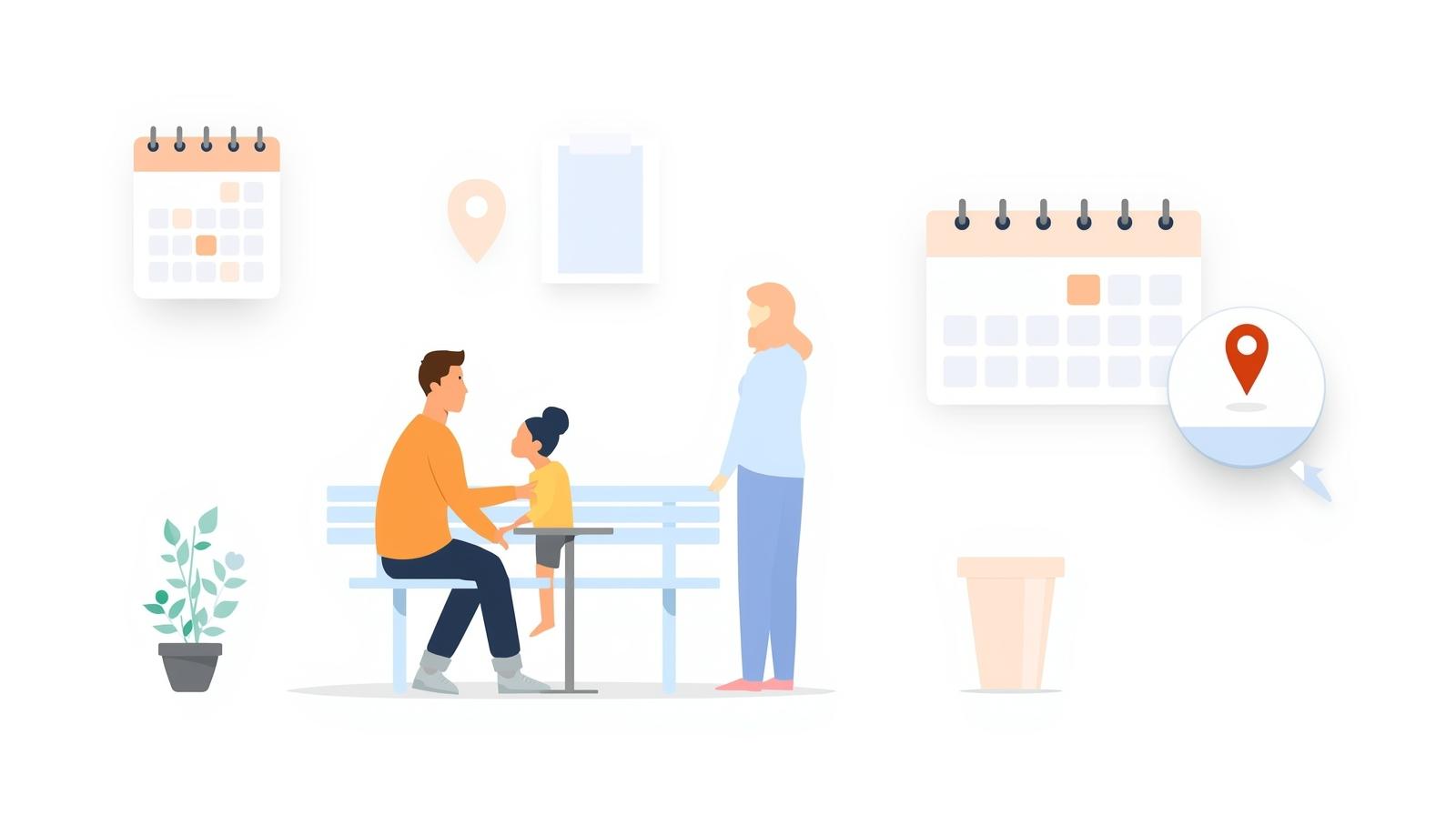

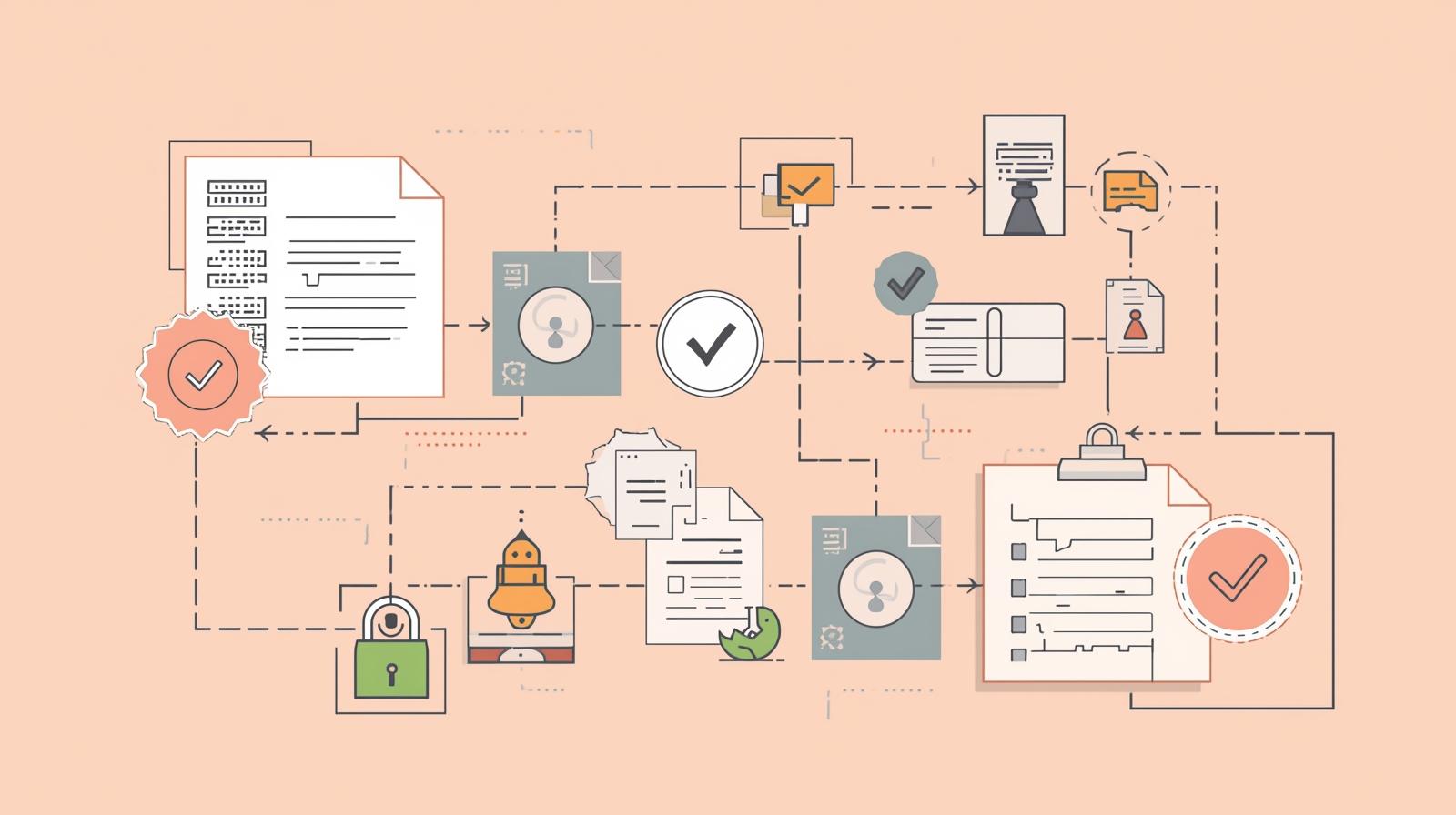
コメント